理不尽で悪質なクレーマーを撃退!初心者でもすぐに使えるクレーム対応術
クレーム対応は初期対応が肝心
まずは初期謝罪で怒りを鎮める






クレームを訴えてくるお客様は感情的になっていますので、まずはお客様の怒りを鎮め、冷静になってもらう必要があります。それに必要なのが初期謝罪です。初期謝罪はお店や会社の過失を認めることなく、お客様の感情を鎮め、話し合いの場を設けるための有効な手段です。
目次
- 初期謝罪で冷静になってもらう
- 不快な思いをさせてしまったことに謝罪する
- 相手の状況に合わせた言葉を選ぶ
- 健康被害は聞き取りよりも相手を気遣う
- 謝罪する際の態度に気をつける
- 初期謝罪にお礼の言葉をつけると効果的
初期謝罪で冷静になってもらう
クレームを訴えてくるお客様の心理状態は、商品やサービスに対する不満が原因で怒りに満ちています。そもそも、会社やお店に対してクレームを出すのは結構な精神的負担があり、それでもクレームを出してきたということは、それだけ怒っているということになります。
そんな心理状態のお客様に対して、「使い方が悪いんじゃないのか?」「言いがかりじゃないのか?」「面倒くさいクレーマーがやってきた」などという気持ちが接客態度に見え隠れすると、たちまち怒りが爆発して、二次クレームとなってしまいます。
また、担当者からの謝罪がない状態でクレーム内容を根掘り葉掘り聞かれることも、お客様が不信感を募らせる原因です。「疑われている」「誤魔化そうとしている」という思いになり、クレーム解決は遠のくばかりです。
怒りで感情的になっているお客様にとっては、疑う余地なく「私は被害者、お店や会社が100%悪い」と考えているため、とにかくこの状況に対して謝罪してほしいと考えています。
そんな心理状態で謝罪されず、取り調べのように質問をされれば、気持ちが落ち着くどころか、怒りがどんどん膨らんでいってしまい、なんとしても謝罪させよう、過失を認めさせようと話が大きくなっていくことがあります。
お客様が怒りに満ちた状況では、担当者がどんなに説明を行ってもお客様に伝わらないどころか、こちらの言葉を受け入れてくれませんので、まずは担当者が謝罪する姿勢を見せて相手の気持ちを落ち着かせ、冷静に話し合える環境をつくる必要があります。
この最初の謝罪を「初期謝罪」と言い、クレームの初期対応としてとても大切なステップとなります。
謝罪の対象はお客様の不快な気持ち
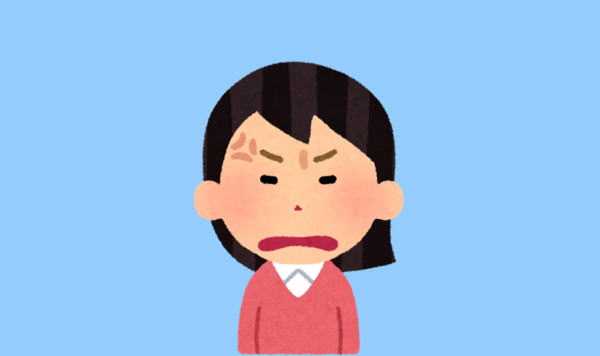
商品やサービスの過失がわからない時点で謝罪することは、商品やサービスに過失があることを認めたということになりますので、過失を認めるような謝罪をしてはいけません。
しかし、まったく謝罪をしてはいけないという訳ではなく、このタイミングではむしろ謝罪の姿勢を見せることが重要です。ここで重要なのは、謝罪の対象を限定した上で謝罪するということです。
お客様は商品やサービスで起きたなんらかのトラブルによって不快な思いをした訳ですから、その後のクレーム処理を円滑に進めるためにも、まずは不快な思いをさせてしまったことに対してしっかりをした謝罪を行います。
「この度は当社の商品でご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした」
商品やサービスに過失がなかった場合、「最初に謝って過失を認めていたじゃないか」と言ってくるお客様がいますが、ここでの謝罪は過失があったことに対してではなく、あくまでお客様に不快な思いをさせてしまったこと、クレームのお手間を取らせてしまったことに対しての謝罪です。
謝罪の内容は限定されていますが、お客様にとっては「謝罪された」という印象が残り、要求の1つである「謝罪してほしい」という気持ちがある程度満たされ、ある程度気持ちが落ち着いた状況で話ができるようになります。
もちろん、過失を認める謝罪をしたと勘違いするお客様もいますので、あとから突っ込まれて上げ足を取られないよう、担当者として何に対して謝罪をしたのかを明確にし、しっかりと理論武装をして向き合う必要があります。
相手の状況に合わせた言葉を選ぶ

ひとまず、お客様が不快な思いをしたことに対して謝罪をしても、怒りが収まらないお客様がたまにいますが、それは謝罪の言葉がお客様に対して正しく届いていないと考えられます。
クレームが発生する状況はさまざまであり、お客様が感じた不快な思いも状況によって異なります。
購入した商品が壊れた場合では、期待していたのに裏切られた、その商品が使えないことで大変な不便をした、記念日のケーキが作れなくなった、すごく時間がかかってしまった、そのせいで仕事に遅れた、など。
このような、さまざまな不快な思いをしたことが今のお客様の怒りにつながっている訳ですから、ただ謝罪の言葉を口にするのではなく、お客様の身になり、どのような苦労をしたのかを想像し、お客様を気遣う気持ち、共感する気持ちを言葉にしながら謝罪する必要があります。
「お時間をとらせてしまい…」
「ご不便をおかけしてしまい…」
「ご負担をおかけしてしまい…」
「せっかく当社製品を使っていただいたのに…」
健康被害は聞き取りよりも相手を気遣う

クレームの内容によっては、なんらかの健康被害を訴えてくる場合もあります。健康被害を訴えるクレームの場合、お客様の被害者意識はより強くなります。
「おたくの商品で指を切った」
「こちらで食事をしてから吐き気がする」
「このサプリメントを飲んでから眠れない」
このような健康被害のクレームを受けた場合、実際に因果関係が認められた場合には補償問題になりますので、お店や会社としてはより詳しく状況を確認したくなります。
しかし、前述のとおりお客様は被害者意識が高まっていますので、ただ根掘り葉掘り聞くだけでは不信感が募っていきます。ここで重要なのは、お店や会社の過失の有無に関わらず、お客様のお身体を気遣うということです。
「お怪我は大丈夫ですか?」
「今のお体の具合はいかがですか?」
お客様は「自分が被害者であることを知ってほしい」という思いがありますので、心配されることで要求が1つ満たされることになります。
聞き取りをするよりも、真っ先に気遣いの言葉をかけて、お客様のお身体に最大限の配慮を行っているという姿勢を強調し、お客様に伝わるようにしましょう。
謝罪する際の態度に気をつける

クレームを訴える手段は、メールや電話、手紙、直接来店などさまざまです。よって、お客様に対して謝罪するシチュエーションもさまざまですが、クレームの内容によっては直接お客様のもとを訪問して謝罪する場合もあります。
その場合、お客様と接する際に一番気をつけなければならないのが、言葉よりも態度と姿勢です。
アメリカの心理学者であるアルバート・メラビアンが提唱した法則によると、話し手が聞き手に与える影響の割合は、視覚情報が55%、声のトーンなどの聴覚情報が38%、話の内容はたったの7%しかないとされています。
つまり、どんなに謝罪の言葉を並べたてても、結局はその本人の態度、つまり身だしなみや立ち振る舞いがすべてを物語るということになります。
そのため、謝罪のためにお客様のもとを訪問する際は、身だしなみや座る姿勢に気をつけるのはもちろんのこと、顔の表情や振る舞い、話し方に細心の注意を払う必要があると言えます。
初期謝罪にお礼の言葉をつけると効果的

クレームを訴えてくるお客様の心情としては「いつも利用しているのに嫌な思いをした」「この店に来るのを楽しみにしていたのに」といったやるせない思いからクレームに発展していることも多々あります。
そんなお客様の心情をくみ取り、初期謝罪にお礼や感謝の言葉をつけると、クレームが円満に解決しやすくなります。
- いつも当店をご利用いただき、ありがとうございます。
- いつも当店をごひいきにしていただき、本当に感謝しています。
- 数あるお店の中から当店を選んでいただき、誠に感謝しています。
お礼や感謝の気持ちを伝えられて、嫌な気持ちをする人はいません。また、感謝の気持ちを伝えられることでクレームを訴えたお客様の気持ちが救われる側面もあります。
そして何より、担当者から予期せぬ感謝の気持ちを伝えられたことで、「自分も何かをしてあげないと」という無意識な返礼の気持ちになります。ここでいうお客様の返礼とは、クレームに対する許しです。
このように、初めは怒りに満ちていたお客様に感謝の気持ちを伝えることで、クレーム解決に向けて大きく前進する可能性が高くなるのです。「お礼の言葉」+「にもかかららず」+「初期謝罪」のように、お礼の言葉をうまく組み合わせて活用してみましょう。
| あわせて読みたいクレームトピックス | |
|---|---|
| クレーム対応の基本的な流れ |  |
| 具体的な解決案を提示して終結させる | |
| 相手の話をよく聞く(傾聴) |  |
| クレーム解決に必要なテクニックを身につけよう |  |
| お客様との距離を縮めるお礼とお詫びの伝え方 | |
| お客様と信頼関係を築いて常連客になってもらうには |  |
| 担当者の印象が成否を分ける |  |
| クレームは顧客を増やすチャンスでもある |  |
| 対応で失敗しないメールの書き方とは |  |

















