理不尽で悪質なクレーマーを撃退!初心者でもすぐに使えるクレーム対応術
原因がわからない状況でのお詫びはNG?
正しい対応方法とは






責任の所在がはっきりしない状況での謝罪はすべきではありませんが、感情的になっているお客様に対して何もしない訳にはいきません。そこで重要なのが初期謝罪です。この初期謝罪の対象は商品やサービスではありませんので、謝罪対象を理解し理論武装をしておきましょう。
目次
原因がわからない状況での謝罪はNG
クレームを訴えてくるお客様は感情的になっていることが多く、すごい剣幕で怒鳴られたり、執拗に謝罪を求められたりすると、ついつい商品やサービスに関するクレーム内容について謝罪してしまうことがあります。
「商品が不良だったようで申し訳ございません」
「こちらの施工ミスだったようで申し訳ございません」
しかし、詳しい状況がわからない状態での安易な謝罪は禁物です。クレーム対応の大原則は「必ず状況確認をすること」であり、商品やサービスがどのような状況だったのか、原因はなんだったのかをはっきりさせることが大切です。
よくわからない状況で安易に商品やサービスの過失を認めて謝罪することは、お店や企業の非を認めたということになります。
あとから非がなかったと判明しても、「謝罪していたじゃないか」「真っ先に非を認めていたじゃないか」と言われ、よかれと謝罪したことを逆手にとられてしまうことになります。
クレームを受けた段階では、商品やサービスに不備があったのか、お客様の使い方が悪いのか、お客様の勘違いなのかが不明であり、原因がわからない状況です。
そのため、初期対応の段階で商品やサービスの名前や具体例を挙げた安易な謝罪はしないように心がけましょう。
お客様の気持ちに対してお詫びする
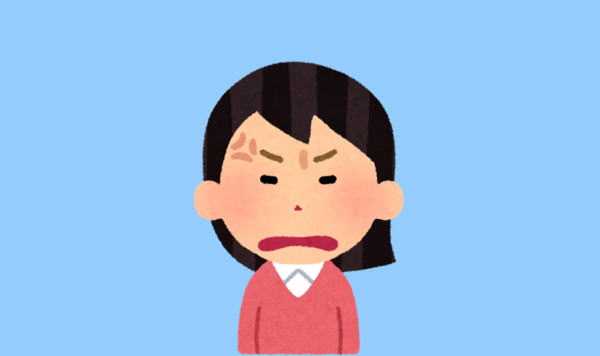
原因や状況がわからない状況で安易に謝罪しないことが大原則ですが、クレームを訴えてきているお客様は感情的になっており、お店や会社からの謝罪を求めてきています。
この段階ではクレームの原因となった過失が商品やサービスにあるのか、お客様に問題があるのかはわかりませんが、少なくとも「自分に原因があるかもしれない」と考えているお客様はおらず、担当者からの謝罪を求めています。
そのような状況下において、担当者がお客様に対して一言もお詫びの言葉を言わないことは、お客様の怒りをさらにエスカレートさせることにもなり、二次クレームにも発展しかねません。
そのため、原因がわからない状況下での安易な謝罪は行わないものの、不快な思いをしているお客様の気持ちに対してお詫びの気持ちを伝えます。
お客様がクレームを訴えてきたということは、原因がどこにあるのかはともかくとして、サービス中に不快な思いをした、商品が壊れたことで大変な不便をしたかもしれません。
お客様はそのやり場のない怒りをぶつけてきている訳ですから、まずはお客様が「嫌な思いをした」「不快な思いをした」「期待に応えられなかった」ことに対してお詫びの言葉を伝えると、その後のクレーム対応がスムーズに運びやすくなります。
謝罪の対象を明確にして理論武装する

クレームを受けた際に、状況や原因がわからない時点では「安易に謝ってはいけない」と従業員教育を行っているお店や会社があります。
クレーム内容がお店や会社に非がなかったとしても、最初に謝ったことで非を認めたことになり、補償や損害賠償を求められるリスクがあるからです。このような傾向はサービス業だけでなく、医療過誤を警戒している病院などの医療施設でも見られます。
しかし、原因がはっきりしない状況でもクレームを訴えているお客様は自分に非があるとは微塵も考えていませんので、謝罪の言葉がなければ怒りがエスカレートすることも考えられます。
そのため、お客様の感情を落ち着かせる意味でも「お客様に不快な思いをさせてしまった」ことに対して謝罪をする訳ですが、クレーム対応する担当者は「初期対応のお詫び」と「正式な謝罪」をきちんと分けて考える必要があります。
つまり、最初のお詫びは「お客様に不快な思いをさせたこと」に対して、正式な謝罪は「商品やサービスの不備」に対してということになります。
仮に原因調査の結果、お店や会社に非がなかったと判明しても、悪質なクレーマーの場合は「謝って非を認めたんだから責任をとれ」と言ってくる場合があります。
しかし、初期対応の謝罪対象を担当者の中で明確にしておくことで、「お客様にご不快な思いをさせてしまったことに対してお詫びをしたのであって、過失を認めた訳ではございません」と、はっきりと相手に伝えることができます。
| あわせて読みたいクレームトピックス | |
|---|---|
| クレーム対応の基本的な流れ |  |
| 具体的な解決案を提示して終結させる | |
| 相手の話をよく聞く(傾聴) |  |
| クレーム解決に必要なテクニックを身につけよう |  |
| お客様との距離を縮めるお礼とお詫びの伝え方 | |
| お客様と信頼関係を築いて常連客になってもらうには |  |
| 担当者の印象が成否を分ける |  |
| クレームは顧客を増やすチャンスでもある |  |
| 対応で失敗しないメールの書き方とは |  |

















